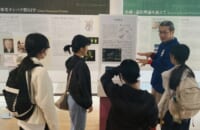世界をデザインする創造力

シンガポールから学び、建築を探究する
建築は、構造的にしっかりしているだけでなく、美しさを含めたまちのシンボルとしての役割を担っています。人々に自信をあたえ、愛着を引き出すような、見る人の想像力をかき立てるものでありたいと思うのではないでしょうか?同志社中学の建築校舎も「なぜこんな形になったのだろう?」と問いを呼び起こしてくれます。2025年から類設計といっしょに、探究(技術)の授業でこの奥深い建築の世界に踏み入れ、実際に手を動かしながら探究しています。1学期には、「小さな都市」としてデザインした本校の校舎を題材にして「どの立場から見るかで、空間は違って見える」ことや、建築家としての観方、考え方の手ほどきを類設計の専門家からまなんできました。校内を歩きながらスケッチを重ね、窓の高さの工夫、メインストリートの奥行き感、ゾーニングによる動線など、普段当たり前に使っている校舎が、じつは緻密な設計思想に基づいてつくられていることなど、たくさんの気づきをいただき、校舎を「学び直」しています。
自由研究が世界へ(佐伯さんの挑戦)
「建築」をテーマに3年間自由研究を続けてきた佐伯さんは、24年にシンガポールで成果を発表しました。アジア各国の中高生が集まる「Global Link Singapore」での舞台でした。「たくさんの刺激とモチベーションをもらった」佐伯さんは現在ニュージーランドに留学され、IBクラスにて勉強されています。
本校で30年続く「ブリッジコンテスト」
橋も同様に、単に荷重に耐えるだけでは十分ではありません。生徒たちは自らの設計に「美しさ」やシンボルとしての役割をどう含みこむかを考えます。実際に強度試験したり、本物の骨材(レンガやコンクリート)を使って実験したり、現地に行って本物の橋を体験したりしながら、社会インフラとしての橋を学んでいます。
アートとエンジニアリングが融合するシンガポールの橋
探究や英語の先に、シンガポールでの発表という体験を中学時代にできるなら、それはかけがえのない経験となります。ぜひ中学時代に佐伯さんのように「Global Link Singapore」での舞台を経験してください。そして、もしシンガポールに行ったなら、美しく個性的でシンボリックな橋を実際に見に行ってください。Jiak Kim Bridge、Robertson Bridge、The Helix Bridge、Jubilee Bridgeを訪れてみてください。中でもThe Helix Bridgeは、波のようにうねる形状をしていて、「え、これ本当に橋なの?」と驚くことでしょう。マリーナベイ・サンズとマリーナセンターをつなぐ二重らせんの歩行者専用橋はDNA構造をモチーフに設計されているとのことです。アートとエンジニアリングが融合したシンボリックなシンガポールの橋を体験は、オーストラリアのKurilpa Bridgeを思い出させてくれます。
シンガポールでは、常識にとらわれない自由な発想から橋や建築が生まれていることを実感できます。シンガポールの革新的な建築との出会い、本校の校舎を教材にした探究、そして生徒が世界で発表する自由研究、いずれも共通しているのは、土木・建築を通じて想像力と社会のつながりを学ぶことだと思っています。(技術科 沼田 和也)